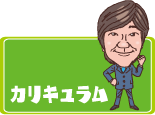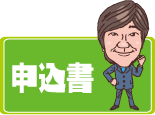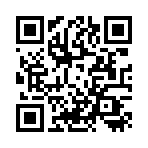2011年05月20日
有能感を育む学童期
みなさまおはようございます。ジュニエコ委員会 小林です(^^)v
心理学者のE.H.エリクソンによれば、
小学校5、6年生は学童期と言われる発達段階にあたり
自分はやればできる!と感じる有能感、
自分はあの子よりもできない・・・と感じる劣等感の形成を課題としている。
従って、この時期に「苦手だ」と自分自身が思ってしまえば
学生時代や社会人になっても後を引くことは容易に想像できるでしょう。
5、6年生のときに「自分は頑張ればできる人間だ」と思うことが
どれほどの宝になるのか、改めて認識をせねばなりません。
自分を信じる=自信を育む中身は2つありますね。
1つは長所を伸ばすこと。
”自分は得意だからできる”と思っていることは、放っておいてもやるものです。
エリクソンによれば、自律性・自発性は早い段階で身につけているとされ
関心があることには積極的に関わり、学ぼうとします。
ですからあまり心配ではありません。
課題は2つ目、短所を補うこと。
”頑張ればできる”と感じていれば、歯を食いしばり踏ん張ることができるのでしょう。
しかしジュニエコに参加した段階であるジャンルに関してはすでに劣等感を抱いている
場合、私たちはどのように接すればいいのでしょうか。
「がんばろうぜ」と背中に手を添えて個人の努力を説くべきか、
「苦手はことは今は敢えて克服しなくてもいい、得意な人に任せよう」
と社会関係を上手く使うことを示唆するべきか、
それともそんなにスッパリと割り切れるものではないのか、
まだ答えは出ていません。
例えば、売上・利益の計算は得意、苦手がハッキリしますね。
すでに有能感・劣等感が芽生えている分野かもしれません。
講師・サポーターはどのように接するべきでしょうか?
また、人に対して立派にプレゼンできる人、恥ずかしがってひっこむ人、
すでに有能感、劣等感が芽生えているかもしれません。
「やればできるじゃん!」と思えるにはどうすればよいのか、
いろいろな疑問が湧いてきます。
運営側の教え方、やり方は個人差があっても良いと思います。
ただ、考え方、目指すことは同じ根っこでなければなりません。
そういう意味でも、一度発達心理学、その一部の児童心理学は
触れておかねばならない領域でしょう。
心理学者のE.H.エリクソンによれば、
小学校5、6年生は学童期と言われる発達段階にあたり
自分はやればできる!と感じる有能感、
自分はあの子よりもできない・・・と感じる劣等感の形成を課題としている。
従って、この時期に「苦手だ」と自分自身が思ってしまえば
学生時代や社会人になっても後を引くことは容易に想像できるでしょう。
5、6年生のときに「自分は頑張ればできる人間だ」と思うことが
どれほどの宝になるのか、改めて認識をせねばなりません。
自分を信じる=自信を育む中身は2つありますね。
1つは長所を伸ばすこと。
”自分は得意だからできる”と思っていることは、放っておいてもやるものです。
エリクソンによれば、自律性・自発性は早い段階で身につけているとされ
関心があることには積極的に関わり、学ぼうとします。
ですからあまり心配ではありません。
課題は2つ目、短所を補うこと。
”頑張ればできる”と感じていれば、歯を食いしばり踏ん張ることができるのでしょう。
しかしジュニエコに参加した段階であるジャンルに関してはすでに劣等感を抱いている
場合、私たちはどのように接すればいいのでしょうか。
「がんばろうぜ」と背中に手を添えて個人の努力を説くべきか、
「苦手はことは今は敢えて克服しなくてもいい、得意な人に任せよう」
と社会関係を上手く使うことを示唆するべきか、
それともそんなにスッパリと割り切れるものではないのか、
まだ答えは出ていません。
例えば、売上・利益の計算は得意、苦手がハッキリしますね。
すでに有能感・劣等感が芽生えている分野かもしれません。
講師・サポーターはどのように接するべきでしょうか?
また、人に対して立派にプレゼンできる人、恥ずかしがってひっこむ人、
すでに有能感、劣等感が芽生えているかもしれません。
「やればできるじゃん!」と思えるにはどうすればよいのか、
いろいろな疑問が湧いてきます。
運営側の教え方、やり方は個人差があっても良いと思います。
ただ、考え方、目指すことは同じ根っこでなければなりません。
そういう意味でも、一度発達心理学、その一部の児童心理学は
触れておかねばならない領域でしょう。
Posted by 掛川YEG at 07:06│Comments(0)
│子どもたちへの教育